私が裁判官になったわけ
札幌高等裁判所長官
合田 悦三(南25期)
去年の7月末に、人事異動で札幌に戻って来た。昭和の終わりごろに札幌で勤務して以来、平成を飛び越し、令和の時代に二度目の道内勤務になったわけだが、この夏には定年を迎えるので、全くの偶然とはいえ、今の職業としては最後になるであろう時期を札幌で過ごせることを嬉しく思って日々暮らしている。冬になって、雪の降る中を歩いていると、楽しくて頬が緩んで仕方ない。道産子であることをしみじみ実感する。
私の職業は裁判官である。この職業に就いてから40年近いので、今では南高関係者の中に知っている人もそれなりにいると思うが、それらの人たちも、最初にそのことを聞いたときには意外に思ったに違いない。なにしろ、昭和50年3月に南高を卒業したとき、私自身が全く想像すらしていなかったのであるから当然である。
そこで、今回は、裁判官になった経緯などを書いてみたい。というのは、私の場合は選択するまでの漂流の程度が他の人より大きかったのかもしれないが、そもそも裁判官というのは具体的イメージを持ちにくい職種である。現在、後輩裁判官の中には南高出身者が増加し、それなりの数になっているが、裁判官志望を決めたのは実際の裁判官の仕事に触れてからだったという者が大多数である。そういう時期になって決まる職業もあるということを紹介し、現役南高生だけでなく大学生になっている後輩やその保護者の皆さんの何かの参考になればと思うのである。
私は、網走市の生まれで、その周辺で育ち、斜里町と摩周湖の間にある清里町というところの中学校を卒業して、いわゆる越境で南高に進んだ。あの頃、そういった子供たちが持つ将来の職業イメージの典型は医師であり、私も同様であった。実は、このとき同じ中学から他の2人も南高に進学し、彼らはいずれも初志を貫徹して医師になっていて、私はそれを誇りに思っているが、自分の方は高1のときに数学と仲良く付き合えないことを悟り、早々と医師になることを諦めてしまった。いわゆる「文転」ではなく、理科系の選択すらできなかったのである。では、文科系志望者として励むしかなかったはずなのだが、何しろ高校に入って半年くらいで、その学校に進んだ理由を見失ってしまったということもあって、大学受験の関係では糸の切れた凧のような状態で身が入らず、生徒会執行部に入り浸って過ごしていたことが多かった。我々が入学したときの3年生は、安保闘争で世の中が騒然とした時期に南高で発生したバリケード封鎖等の出来事を1年生として経験した世代であったこともあり、当時の南高には、学校全体の雰囲気や学校側と生徒側との関係性に独特のものがあると感じられた。生徒側には自主性の意識が強く、学校側も基本的にそれを尊重する姿勢を示してくれていた(もちろん、今の年齢になれば、それは学校側が根本において自校の生徒を信頼し自信を持っていてくれたからでこそだったと理解している。)。時には学校側に苦情を述べたこともあった。他方で、その頃は弱小であった野球部が予選を勝ち進んだときには、「明日の午前中の授業をやめて全校応援をさせてほしい」と突然願い出て許可してもらい、当時南高の近くにあった中島球場で応援したこともあったし、旧制札幌一中の名物行事である雪戦会を復活させることもできた。文化祭が近くなると様々な折衝や準備に追われ、時には私の下宿に集まって徹夜作業をしたこともあった(このときは、高校生ながら神経性胃炎になってしまうというおまけもあった。)。数年前の東京六華同窓会で卒業以来の再会を果たした同期生に「君は、難しい本を持ち歩き、あらゆることに怒っていた」と言われたが、前半は倫理・社会担当の本多先生が読むべきだと言われた岩波文庫を買うだけは買っていたことを指しているのだろうと見当はついたものの、いろいろなことはあっても楽しく過ごした記憶の本人としては、後半部分には「そうかなあ」としか返せなかった。
そのようなわけで、高3の時には甚だ困惑した。なりたい職業像を持っていないので、格別進みたい学部もない。しかし、大学受験は着々と迫ってくる。仕方ないので父親に相談してみると、「潰しがきく」という理由で、「取りあえず法学部に進んでから、その先を考えてみてはどうか」と助言してくれた。そこで、不真面目な受験生でもなんとか現役で合格させてくれた中央大学法学部に入学したというのが南高卒業時の実態だったのである。
大学1年生のときは、体育連盟の部活動と戯曲を研究するゼミの活動に没頭したが(ちなみに、後者は、今の演劇・演芸好きにつながっている。)、転機は2年生のときに訪れた。「暇だし、法学部だから、一度くらい裁判傍聴をしてみるか」という気まぐれを起こして、東京地裁に行ったのである。そこで傍聴したのは、盗みで初めて裁判を受ける若い男性被告人の事件であった。被告人は罪を認めており、母親が泣きながら「優しい子なんです」と証言した後、被告人への質問が行われたが、そこで驚いた。最初に質問した年配の弁護人(弁護士がなる)がひたすら被告人を叱り、被告人は号泣しながら反省の言葉を繰り返しているのである。「法律の勉強をろくにしていない自分だって、弁護人が被告人を守る立場にあることくらいは知っている。それなのに、この弁護人は被告人を責め、いじめている。こんなことが許されていいはずがない。よし、自分が弁護士になって被告人を守ろう」、単純な私はそう考えたのである(ちなみに、今にして思えば、このときのシーンは、先回りして自らが追及することで、被告人に対する検察官の質問を和らげようとする弁護人の作戦であったのだが、そんなことは思いもしなかった。やはり、すべてに立腹するタイプだったのだろうか・・・?)。
法律実務家(弁護士、検察官、裁判官)の資格は国家資格であり、それを取得するオーソドックスな方法は、司法研修所で司法修習生の卒業試験(これが国家試験になる)に合格することである。そして、司法修習生に採用されるためには司法試験に合格する必要がある(よく誤解されるが、司法試験に合格して得られるのは、法律実務家の資格ではなく司法修習生に採用される資格である)。そこで、上記のとおり「決意」した私は、司法試験の勉強を始めた。現在は、学部から法科大学院(ロースクール)に進んで卒業するか、予備試験というものに合格するかのいずれかのルートで司法試験の受験資格を手に入れる制度になっているが、当時は大学の教養課程を終わった3年生から受験資格があった。その頃の合格率は2%前後だったように思うが、これは単純に合格者数の受験者数に占める割合というだけのことである。勉強を重ねて実質的な意味で競争に参加できるレベルまで至ってみれば数倍程度に感じられた。もちろん、それでも最難関と言われるに相応しい試験には違いなく、落ちたら弱点を補強して翌年チャレンジすることを繰り返さなければならない。私は、幸運にも恵まれ、結局、大学を卒業した年の3回目の受験で合格したのであるが、その年の最終発表の前夜に「今年も多分ダメだろうが、これで落ちたら来年はどうやって勉強したらいいのか見当がつかない」などと思って暗い気分に陥っていたのを昨日のことのように覚えているから、自分を相当追い込んでいたのであろう。我が人生で最も受験勉強に打ち込んだのは間違いなくこのときである。
司法試験は、法律の試験であり、これに合格すれば法律実務家に必要最少限度の法律知識はあることなるが、それだけでは使い物にならない。例えば、貸した金を返す返さないという紛争はたくさんあるが、そこで使われる法律は「借りた金は返さなければならない」と「返した金は、もう重ねて返す必要はない」程度のことで、内容が明白で解釈の余地がないルールである。しかし、ほとんどの事件では、金の貸し借りがあったかどうか、既に返したかどうかといった「ルール適用の前提となる事実関係」が争われ、それがどうなるかだけで決着がついてしまう。「証拠による証明」とか「事実認定」と言われる領域であり、そこを学ばなければならない。そのため、司法試験で問われなかったその他の実務で必要な知識や技術的な面も含め、司法修習において、司法試験合格者に対して、それらの点を教育した上で、卒業試験(司法試験から数えて2回目なので通称「二回試験」)をして、合格した者に法律実務家の資格を与えることとしている。
この司法修習のカリキュラムは、弁護士、検察官、裁判官の下で実際の事件を通じて学ぶ「実務修習」を中核としており、司法修習生は全員、三つの立場のすべてについて実務修習をしなければならない。三つの法律実務家が実際にはどのような仕事をしているのかに直接触れるのであるから、司法修習生にとって、学びの機会であると同時に職業選択に関する重要な情報を得る機会でもある。私の場合は、弁護、検察、裁判の順番であった。
私は裁判傍聴の経験から弁護士になろうと思って司法試験を受けたのであるから、弁護修習は自分の将来像であった。様々なもめ事を抱える人々の相談に応じ、その人の権利・利益を守るために、解決の方策を提案・助言し、相手方との交渉や裁判手続を通してその実現を図るために働く。刑事事件では、推定無罪(疑わしきは被告人の利益に)の原則が実現されるように、被告人のために活動する。人々に寄り添い社会正義の実現を目指す。そういう仕事であることを実感して弁護修習は終わった(ちなみに、修習生時代に経験したわけではないが、時に、弁護士が悪い者の肩を持っているとの批判を受ける場合もある。しかし、世の中はなかなか複雑で、一方だけが100%悪いと言い切れるケースは相対的に少ないし、仮に100%悪くとも言い分があるならそれを主張する機会は保障されなければならず、それを圧殺することは近代社会の価値観からすれば不正義である。また、最終的に採用するかどうかはともかく、様々な視点からの主張が展開されることは判断者である裁判官にとって基本的に有用である。)。
そういうことで、弁護修習から検察修習に移るときには敵地に乗り込むような気持ちがないでもなかったが、修習をしてみると持っていたイメージが完全に打ち砕かれた。検察官は、必要に応じて被疑者や参考人から話を聞き、他の証拠と総合して、起訴する(裁判にかける)かどうか判断するが、その判断は推定無罪の原則の下で行われると同時に、証拠が十分であるとしても処罰することが適切かという見地も踏まえて行われる。そして、起訴した事件については、有罪の立証ができ処罰に値する事案であると判断した以上、裁判で適正な処罰が行われることこそが正義の実現であるとの考えに基づいて、それに向けた活動を公判において行うのであって、弁護士とは別の側面から社会正義の実現を目指す仕事である。当時は、今のように犯罪被害者保護という点に社会の目が向いていなかったが、検察内部では「被害者とともに泣く検察」という言葉が強調されていて心を動かされた。また、当時の私は、社会治安の維持と聞くと何となく強権的なイメージを持つ感覚があったが、考えてみれば、安全・安心な暮らしや社会の安定というのは一般国民の誰もが望んでいるところであり、犯罪が頻発している社会治安の乱れた状態ではそれが叶わないのであるから、犯罪者に適正な処罰が行われるように活動することには意味がある。検察修習が進むうちに、自分でも驚いたことに、検察官こそ自分の天職ではないかと思うようになり、最後の裁判修習が始まる頃には、内心では9割方検察官になろうと思っていた。
ところが、裁判修習をしているうちに迷いが生じ始めた。この頃までには、単純な「決意」で目を向けたとはいえ、法律実務家としてやっていきたいという気持ちは揺るぎないものになっていた。法律実務家は、実情を知れば知るほど魅力的な職業であり、自分もその中に加わって、社会正義の実現に寄与したいし、何より少しでも人の役に立ちたいと思った。しかし、社会正義が実現されるとはどういうことか。例えば、刑事裁判で見れば、推定無罪の原則の下では、有罪であることに間違いないという証明がされるに至らなかった場合は、それがどれほど疑わしくても無罪にならなければならないし、他方で、推定無罪の原則の下でも有罪と判断される場合には、必要があれば峻厳なものになる場合を含めて犯人を適正に処罰することにより安心・安全な暮らしや社会の安定が図られなければならず、これらがいずれも達成されなければ社会正義が実現されているとは言えないであろう。そうすると、結局のところ、判断者である裁判官が個々のケースで適正な結論を出さなければ社会正義は実現されないのではないか。大変に責任の重い仕事であるが、それだけにやりがいは大きいであろう。自分にそれを務めるだけの能力があるかどうか自信はないが、せっかく法律実務家を志したのであるから、自分は判断者の役割を担ってみたい。青臭く思われるかもしれないが、本当にそう思うようになっていった。決めつけをせず「そういうこともあるかもしれない」というスタンスで耳を傾け結論を模索する裁判官の姿勢に触れたことも影響したのかもしれない。だが、そう思いつつも、自分に一番向いているのは検察官ではないかという思いもなくならず、採用の願書を出す直前まで揺れ続けた。そのような時期まで志望が決まらなかったという話を他に聞いたことがないくらいである。それでも、最後は、社会正義の実現により直接かかわることのできる仕事に加わりたいという気持ちが勝って、裁判官の採用願を出し、判事補として採用された。昭和57年のことである。
それから40年近くが経過し、自分の裁判官としての種類も、判事補から判事を経て高等裁判所長官に変化したが、その間、裁判官になったことを後悔したことはただの一度もない。その最大の理由は、この職業の精神的自由さにある。判断者というのは責任が重い立場であり、結論に到達するまでに相当悩む。適切な結論を出して当たり前で誰も褒めてはくれず、裁判に負けた側から非難されることも珍しくはない。しかし、裁判官には、どちら側を勝たせなければならないというバイアスは全くない。そこが勝ち負けのある検察官や弁護士との決定的な差である。証拠に照らして事実を認定し、それに法律を適用して結論に至る。その過程で悩むことがあったとしても、その結果到達した自分がベストと思う結論を示すことで役割を果たしたことになる。まさに日本国憲法76条3項が「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法と法律にのみ拘束される。」と規定するとおりの職業なのである。この点は、裁判官なら誰でも挙げるかけがえのない魅力である。もう一つ、人の役に立っているという自負を持てるという点もある。裁判所は、法律的に紛争の最終決着を付ける公的権限を有する唯一の国の機関であり、その判断が確定すれば、法律上は勝った方も負けた方もそれを受け入れなければならない。これは、紛争をいつまでも引きずっているのは決して双方にとって良いことではないので、裁判所の判断が確定した時点で争い続ける余地をなくして、双方にそれを前提とする安定した生活を将来に向かって送ってもらうためにそのような制度を設けているのである。つまり,裁判官は、判断を示すことで、双方の安定した将来の生活の実現に資することができるのである。
裁判官という職業について書きたいことはたくさんあるが,もはや、相当な長文をお読みいただいているので、本稿はここで閉じる。が、現役南高生や既に大学生となっている皆さんには、是非一人でも多くの方に、法律実務家という職業にも目を向けていただきたい(法科大学院と予備試験のいずれについても、法学部以外で合格した例が多数ある)。人がいる限り、将来も必ず紛争は起こるから、その解決に携わる法律実務家は必須であり、困った人たちがあなたの力を求めている。やりがいにあふれた仕事である。
そして、法律実務家を志望することになったら、是非裁判官という選択も考えてください。きっと後悔しない職業選択になると、今は裁判官が天職であったと確信している私が請け合います。まだまだ十分に間に合いますから。
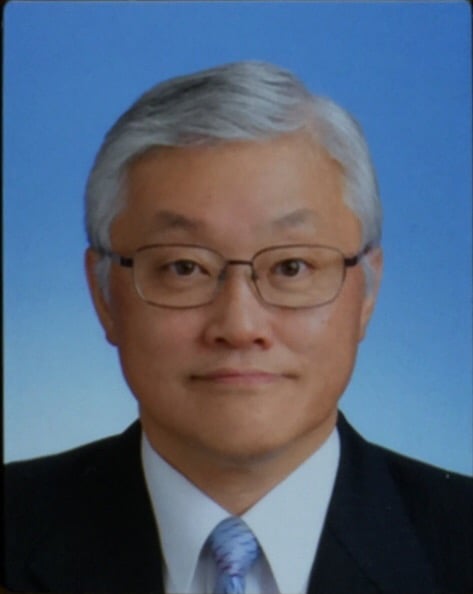 合田 悦三(ごうだ よしみつ)
合田 悦三(ごうだ よしみつ)
中央大学法学部卒。裁判官として、東京地裁、札幌地裁、仙台地裁で勤務。その間に、1年間の民間研修なども経験。さらに、司法研修所教官や最高裁刑事局課長を経て、平成14年から同27年まで東京地裁において部総括(裁判長)や所長代行者を務める。同年前橋地裁所長、同28年東京高裁部総括(裁判長)、同31年千葉地裁所長、令和2年7月から現職。裁判員制度に構想段階から関与し、実施後は自らも裁判長を務めた。






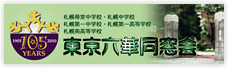


第98号 の記事
2021年3月1日発行