堅忍不抜の精神について
澤田展人(南22期 元南高教諭)
始めに
札幌南高校の伝統的精神は「堅忍不抜」である、と言われる。
「堅忍不抜」とはなんであろうか。辞書を調べると「かたくこらえてぐらつかないこと」(『日本国語大辞典』)とある。困難な状況にあっても心を乱さずじっと耐え、おのれの志を保つような人間のありかたであろうか。
「堅忍不抜」は、旧制中学時代の校歌と新制高校になってからの校歌のどちらにも共通して使われていることばである。だから、旧制中学から新制高校を貫く伝統的精神を探し求める人は、「堅忍不抜」にその答えを求めるのだろう。
ちょっと歌詞を見てみよう。まず旧制中学の校歌から。この校歌は作詞者大和田建樹である。大和田は『夏は来ぬ』や『鉄道唱歌』を書いた著名な詩人・作詞家である。十周年を迎えた札幌中学が記念の校歌をつくるために大和田に作詞を依頼したのだろう。
五番に「堅忍不抜」が出てくる。「堅忍不抜の精神は/年の半ばを降り埋む/雪の下にも春待ちし/百花と共に顕れむ」。六番も引用する。「地の利を占むる北海の/前途はいやまし多望なり/いざもろともに報国の/心一つに進取せん」。「堅忍不抜」と「報国」がセットになっていることに注意したい。
つくられたのは明治39年(1906年)、日露戦争の直後である。学校教育においては、ナショナリズムの高揚を背景に、志操堅固で国に尽くす人間になることが理想視されたのであろう。
札幌第一中学校に
札幌中学校から札幌第一中学校と変わり、本校は徐々に、バンカラ精神の横溢した男くさい学校になっていく。そのことがよくわかるのはなんと言っても雪戦会である。始まったころは素朴な城とり合戦の行事だったが、やがて城づくりも戦闘法も組織化され、出血・骨折・人事不省に陥る者が多数出る壮絶な行事になった。勇壮を越えて凄惨な様相を呈すこともあった。この行事へかける生徒の意気込みはすさまじく、見物に来る市民の興奮もただものではなかったと言われる。
生徒が困苦に耐えけがを怖れず自軍のために尽くす雪戦会は、「堅忍不抜」の精神を発揮する恰好の場であったろう。一方、雪戦会に代表される札幌一中の男くささを嫌がる者は、札幌二中を選んだという。繊細な精神を必要とする芸術や文学の領域で名を挙げた者が、二中出身者に多いと言われるのはそのためか。
第二次大戦終結に至るまで本校において、「堅忍不抜」は、不動の精神という本来の意味に加えて、ふだんは我慢強く平静を保ちながらも、いざというときには勇猛果敢に戦う「男らしさ」の意味合いをもったように思われる。男子校である旧制中学に多く見られるマッチョ的な志向がそこに感じられるし、皇国思想のもとで尽忠報国の色彩も加えていったことは否定できない。
敗戦後の母校と堅忍不抜
敗戦によって、学校制度は一気に変わった。米占領軍指導下の教育改革で、本校は男女共学の新制高校に生まれ変わった。戦前の学校体制の大半が変更された。校歌も昭和26年に新しい歌詞が決められ、発表された。作詞者は、一中の卒業生でもある戸津高之教諭である。戸津は「私の考えたのは古いものも伝え、新しい気分をも取り入れて、時代に即したものにしたいということであった」と「札幌南高新聞」第3号で語っている。
戸津が意図した、古いものを伝えることは、校歌二番に実現されている。引用してみよう。「年の半ばを降りうずむ/雪にきたえし精神は/堅忍不抜ゆるぎ無き/わが先人の旗印/ああつぎ行かんこの誇り」。雪国の厳しい気候に耐え抜くことで形成された不動の精神を、本校の先人が残した伝統ととらえ、これを受け継いでいこう、と決意を示した歌詞である。
旧校歌と共通する「堅忍不抜」ということばを取り入れることで、戸津は、旧制中学札幌一中から新制高校札幌南高へと様変わりした学校の間を架橋しようとしたのではないか。精神においてつながるものがあってほしいという願いを歌に込めたのだろう。
その思いは実現したのか。
戦後教育制度の変遷の中で、札幌南高は、かつて札幌一中がもっていたエリートが集う学校の位置を再び占めるようになっていくのであるが、他校と比して「堅忍不抜」の精神が際立って実現しているかどうかは、判断のしようがない。
私などは、「堅忍不抜」をわざと「けんにんふぬけ」と読んで、伝統校・エリート校を誇るような雰囲気に逆らう生徒であった。そのような人間であることを断った上で、ここで、「堅忍不抜」を「おのれの志をしっかり保ち、ゆるがぬ精神で事に処すること」という本来の意味に解し、そのような精神に当てはまる人物を、先人や同輩の中に探してみた。
堅忍不抜の人々
西田信春 きちんと出ていってきちんと帰ってきた男
まず、西田信春(1903~33)である。西田は新十津川村に生まれ、札幌一中を卒業後、一高、東大へと進学した。一中時代の友人は、西田が、国語や漢文の時間、美しいはずみのある声で読み上げ、休み時間には校庭で草野球の名手だったと回想している。一高、東大ではボート部に入り筋骨隆々の体をしていた。左翼組織東大新人会に加入し、卒業後は労働組合の書記として活動する。労働者階級を解放するために一身をささげようと決心しながらも、肉親に対する愛情と思いやりを濃厚にもった人だった。1933年、九州で共産党の活動を行っていた西田は福岡署で取り調べを受けている最中に急死した。死後20年を経過して、遺体を解剖した医師の証言から、取り調べ中の拷問がもとで死にいたったことが突きとめられた。
西田と親しかった作家の中野重治は次のように記している。「怒りっぽくない人間、どんな意味からも毒々しいところの微塵もない人間、ごく自然に見栄っ張り、虚栄心のなかった人間、首をまっすぐにして本を読み、記録をつくり、きちんと出て行ってきちんと帰ってきた男、言葉でも書くものでも誇張ということをしなかった人間、騒がしさ全くなしに快活だった強健な肉体の持主、あんな男が、失われたことが残念なだけでなくこれからこそ必要なのだろうと痛切に思う」。
村中孝次 2・26事件の真相を世に残した勇気と胆力
次は村中孝次(1903~37)。村中は旭川の生まれ。父の仕事の都合で札幌に移り、西創成小学校を卒業後、札幌一中に進学。間もなく両親が逝去し、村中は1年を修了後、仙台の陸軍幼年学校に入学。その後、陸軍士官学校を卒業し、旭川で少尉に任官。初年兵の教育係となり、兵士の身上調査を通じて米も食べられない農民の窮状を知るようになる。昭和6年の冷害による凶作により、農民は飢餓に陥り、青田を売る者、娘を身売りする者が多数出た。地方にいてはこの問題を解決できぬと考えた村中は、陸軍大学に合格し上京する。皇道派青年将校グループの中心的人物となり、政財界軍部刷新のために蹶起する。世に言う2・26事件である。クーデター失敗後、山下奉文少将が陸相官邸で青年将校たちに、切腹による自決を呼びかけ、一同自決せんとするときに、村中は「死は易く、生は難い。公判を通じて広く国民に訴えてから死んでも遅くはない」と述べた。山下少将の言に従っていたら関係の青年将校は全員自決し、事件の真相は闇から闇に葬られるところであった。
村中は公判で死刑を宣告され、1937年、磯部浅一、北一輝、西田税らとともに銃殺刑に処された。村中の知人は、「真に勇気と胆力のある者は、ふだんは平静温厚でめったに覇気を外に表さないというが、村中は正にそれにピタリの男であった。第一頭が冴えている。文才も豊かで努力家で勤直、人間に深みがあった。後輩や教え子が彼を慕ったのは彼の人間的な深みに魅せられたからである」と語っている。
西部邁 外れ者の自覚を貫いた表現者
続いて、西部邁(1939~2018)。西部は長万部の生まれ、札幌に移ってきて、信濃小学校、柏中学校を経て札幌南高校入学。東大在学時に左翼学生運動の主要活動家となり、60年安保闘争の指導者として逮捕される。その後経済学の研究者となり、東大教養学部長を務めるが、中沢新一を助教授に抜擢する件で学部内がもめ、辞職。保守の立場を鮮明にし、『表現者』という雑誌を拠点に言論活動を展開する。自死の最期までメディアで注目を浴び続けたその生涯は多くの人が知るところである。
左翼から保守へとスタンスを変えたことからすると、西部に「堅忍不抜」は当てはまらないのではないか、と思われる方に次の文を読んでいただきたい。本校百年史に西部が寄せた回想の一部である。
札幌南高校、それは私に外れ者の自覚を、というよりも諦念を、与えてくれた有難い場所だ、というと我が同窓生は怒るだろうか。どうか怒らないでいただきたい。同窓会なるものにいささかの関心も持てない私ではあるが、私は私のやり方で四十年前の記憶を大事にして生きているのである。青春前期に私を襲った「不安な情熱」ともいうべきあの感情が私の現在の言論活動を支えている。それにもとづいてしか言葉を紡ぐことができないという意味で、私の言霊は依然として札幌南高等学校のあたりを彷徨っている。
高校生のときに襲ってきた不安な情熱を生涯の支えとしてきたという西部は、自分の中の変わらぬものを「外れ者の自覚」だと語っている。それは無自覚に大勢になびいていくことをおのれに禁ずる自主独立の心ではないか、と私は思う。実は、日本で保守を標榜する多くの人々に欠けているのがこの自主独立の心である。西部は、近隣諸国に対しては上から目線で強硬な言論を展開しながら、アメリカに対しては服従的な姿勢に終始する右翼言論人とは袂を分かった。イラク戦争開始時に、アメリカに追従するほかなかった小泉政権に、保守の立場からまっとうな批判を行った西部は、思想家として実に首尾一貫していたのである。
外岡秀俊 現場を重んじる「鉄砲玉派」のジャーナリスト
最後に外岡秀俊(1953~)。外岡は札幌生まれ、本校を卒業後、東大在学中に小説『北帰行』で文藝賞を受賞し、一躍注目を浴びる。卒業後は、朝日新聞の記者となる。ニューヨーク、ロンドンなど海外勤務の後、東京本社編集局長を務めた。定年前に退職し、在野のジャーナリストとして活動中。彼は、事が起きたときまずは現場に駆けつける記者を「鉄砲玉派」と呼び、自分もその一人であると言う。記者として湾岸戦争、ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争の現場を経験している。阪神・淡路の震災があったときには、長期間被災地で取材を行った。その後も取材と調査を続け、『震災と社会』(みすず書房)という浩瀚な書物にまとめた。また、東日本大震災の際にも、直後から被災地に入り、現地の状況を取材した。その成果が『3.11複合被災』(岩波新書)、『震災と原発 国家の過ち』(朝日新書)である。
現場を見、現実の状況を伝えることを重視する外岡は、新聞社を退職後も、札幌に拠点を置いて、一介のジャーナリストとして活動している。日本では、大手メディアの記者と在野ジャーナリストの立場は画然と分かれている。取材体制、発表機会、身分保障、どれをとっても、大手メディアに優位性がある。そうした状況において、「鉄砲玉派」を自任する外岡が、退職後も取材に精力を傾け、発信を続けていることに、「堅忍不抜」の精神を感じるのである。
以上にとりあげた人物たちの志操を見るとき、本校が、各自に固有な「堅忍不抜」の精神を生み出す揺籠の役割をしたのは間違いないことだと感じる。

澤田 展人(さわだのぶひと)
1954年生まれ。1972年、札幌南高を卒業。南22期。東京大学文学部宗教学・宗教史学科卒業。民間会社勤務の後、北海道で高校の教員となる。網走、夕張、札幌で勤務。札幌南高の全日制・定時制の両課程で17年間勤務。30代から小説を書き始め、著書に『魂の歌手』、『ンブフルの丘』(2018年道新文学賞作品)がある。2015年教員を退職し、現在、養育里親と市民講座「読み直す高校倫理」の講師をしながら、個人文芸誌「逍遙通信」の編集・発行をしている。






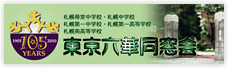


第98号 の記事
2021年3月1日発行