カムバックサーモン!鮭酒叫べ!咲けベイベー!
大橋 誠(南44期)
南44期卒業の大橋 誠です。今、千葉県で酒蔵を建てようともがいています。まだ建設予定地の開墾作業中であり、柱の一本も立っていません。けれども、共感と応援の声を驚くほどたくさんいただくのです。もともと僕はツバメに憧れるモグラのような存在。ありがたい声に恐縮しながらも、僕にできることを探して今日も土を掘っています。
土を掘っているのは本当。僕は農家なのです。10年ほど前、千葉県の多古町という田舎で新規就農しました。米をつくっています。図らずも今、米は話題の中心にあるようです。米が高いと。一方で、米農家の時給は10円なのだそう。そんな様子を、渦中にいながら遠目で眺めています。
さて、酒蔵です。僕はこんな酒蔵をつくりたいのです。
『僕らの酒造りは自然豊かな田舎の蔵で、薪割りから始まります。蔵の熱源はすべて、薪を燃やした炎です。斧を持って、自ら割る。汗をかいて頑張ると、コツが分かってきます。それが楽しい。お酒の原料は、自分たちが汗して育てたお米です。麹菌も酵母菌も、田んぼから採取します。だから、田んぼが健康でなくてはなりません。ではどうすれば…と考える。自分で考え、自分で決める。自治の精神が大切です。
酒は自然からの贈りもの。だから、自然と向き合ってきた先人の知恵に学び、薬品を使わずにじっくり発酵させます。そして酒造りは一人ではできません。仲間と力を合わせ、楽しく汗をかくのです。こうして造ったお酒には、喜びが満ちています。乾杯にも、豊かな気持ちが溢れます。これが私達の考える、豊かな酒造りです。』
昨年暮れに、僕を含めた5名で法人を立ち上げました。「労働者協同組合 鮭酒造」です。労働者協同組合は2022年の秋に国会を通過した新しい法人格。労働者が経営者であり、出資者でもあるという法人です。僕は代表を務めますが、代表だからと言って権力はありません。5人で膝をつきあわせ、きちんと話し合ったうえで一歩一歩進みます。組織の中に偉い人がいて、皆はその人の言うとおりに働くという普通を変えたくて、この法人格を選びました。
ちなみに、メンバーの一人に同級生の渡邊 航君がいます。ラグビー部で共に汗を流した仲間です。面白いことに、今でもラグビー部での役割が同じなのです。僕はフォワード、彼はスクラムハーフでした。僕がボールを持って突進し、捕まってどうしようもなくなると、彼が走ってきてボールを仲間に展開してくれる。この役割が、鮭酒造でも全く同じなので笑ってしまいます。

さて、鮭酒造の鮭です。多古町には、町を南北に貫くように流れる川があります。栗山川です。ここは多古米という銘柄米のある米どころですが、栗山川の水が米作りを支えています。そして栗山川は鮭が遡上してくる川であり、鮭が遡る川としては、太平洋側における南限と言われています。
ところで、北海道で育った皆さんですから、鮭が生まれた川に戻ってきて産卵することをご存じかと思います。けれども、その理由について考えたことはありますか?
鮭は地球の物質循環に大きな役割を果たしていると言われています。雨に溶け、川を伝って海に流れてしまう大地の栄養分やミネラルを、鮭がまた大地に戻す。その大切な役割を担っているというのです。約4年に渡って海で成長した鮭の体には、大地から海に流れ出た養分が蓄えられています。その鮭が自分の生まれた川に戻って動物に食べられたり、土にかえることで、海に流れた養分を大地に戻す役割がある、ということです。鮭の栄養が森を育て、その森がまた海を豊かにする。このめぐりめぐる地球の物質循環における重要な役割を、鮭が担っているのです。何とありがたいお魚でしょうか。アイヌ民族が鮭のことを「カムイチェプ」、神の魚と呼んでいますが、本当にその通りだと思います。
そんな素晴らしい魚、鮭が帰ってくる最南端の川、栗山川流域の酒蔵として、私達は団体の名前に「鮭」をいただきました。鮭のように、私達も地球を豊かにする存在でありたい。そしていつの日か、栗山川にたくさんの鮭が帰ってくるような、豊かな社会を取り戻したい。そんな願いを込めました。
酒蔵ができたら、そこを拠点としてやりたいことがいくつもあります。その一つが「酒造りの自由を実現する」ことです。実は、日本は稀な国なのです。国民に酒造りを禁止しています。宗教上の理由を除けば、そんな国は世界中探しても日本だけです。しかも、新しい日本酒蔵を新設することも許されていません。
それはなぜか。戦争のためでした。1894年(明治27年)に日清戦争が始まり、1904年(明治37年)に日露戦争がありました。戦争には金がかかります。そこで日本政府は財源を確保するために酒税を3.5倍につり上げました。しかし国民が自宅で酒を造ってしまえば税収は上がらない。そこで自家醸造も禁止としてしまったのです。結果として、自家醸造が禁止された1899年(明治32年)の国会歳入の第一位が酒税(35.5%)となりました。しかし、そうまでして続けた戦争の結末は、皆さんご存じの通りです。
しかし、これほど残念なことがあろうか、と思うのです。「酒造りの禁止」です。なぜなら、酒造りは楽しいからです。こんなに楽しいことがあるだろうか、と。僕が造り酒屋の蔵人として酒造りを始めて15年以上が経過しました。ひょんなことから始めた酒造りでしたが、結果として僕は三軒もの酒蔵を渡り歩き、それでは飽き足らず、そもそも酒蔵を建てようとしているのです。酒蔵を建てたら、この楽しい酒造りを一人でも多くの方に楽しんでいただきたい。そして、豊かな気持ちになってもらいたい。そんな風に思っています。
昨年末に、クラウドファンディング事業に挑戦しました。「酒造りは楽しい!みんなの酒蔵を建てます!」と銘打って。その結果、何とありがたいことに、多くの南高卒業生からご支援をいただいたのでした。僕の同級生だけではなく、出会ったことのない先輩方からのご支援もありました。370万円ものご支援金が集まりました。本当にありがとうございました。
この冬もまた、クラウドファンディングに挑戦します。僕が以前蔵人として働いていた千葉県御宿町の酒蔵で、返礼品の日本酒を造ります。今回のご支援金で、僕らは丸太を製材する製材機を購入したいと考えています。酒蔵を建てる際に使用する木は、地元の有志から無償で提供していただきます。これを製材し、地元の木材で地酒蔵を建てるのです。
酒蔵の建設までには、越えなければならないハードルが次々待ち受けているのですが、これを乗り越えることが楽しいこと、楽しい人生なのかもしれません。仲間たちと共に精一杯楽しもうと思います。応援をよろしくお願いいたします。そしてもしよろしければ、一緒に活動しませんか?応援団も、鮭酒造のメンバーも常に募集中です。よろしくお願いします!
詳しくはこちらから 鮭酒造公式LINE QRコード


千葉県香取郡多古町で就農。米農家。労働者協同組合 鮭酒造(さけしゅぞう) 代表理事。
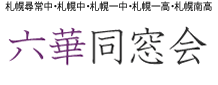

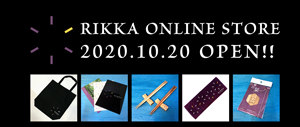


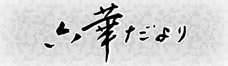
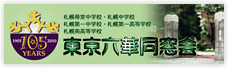

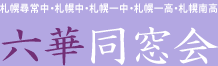
第107号 の記事
2025年10月1日発行