「ルーツ探し」はライフワーク
見延 典子(南24期)
十年程前に「頼山陽ネットワーク」というホームページを立ちあげ、ブログも併設し、ときどきルーツの話を書くようになった。
父方の祖父母、母方の祖父母、つまり四人の祖父母の先祖については明治期に福井県、山形県、石川県、徳島県から北海道に渡ったという話は伝え聞いていたが、それ以上のことは知らなかった。
まずブログに書いたのは父方の祖父見延松吉のルーツについてであった。書きはじめてほどなく、思わぬ反応があった。福井県越前市在住の「見延清左衛門さん」からメールが届き、「見延という姓の者は、必ず自分たちが暮らす集落につながる」と書かれている。
メールでのやりとりを続け、実際に福井県越前市を訪ねて見延清左衛門さんはじめ、同じ集落に暮らす見延姓の皆さんにお会いした。見延松吉の父、つまり私の曽祖父見延梅吉は農家の長男であったが、明治二十年代ころ札幌に出稼ぎにいって定住し、福井の家は次男が継いだ。その次男の子孫とも会うことができた。
この地域では1705年(宝永2)から年一度「惣田正月十七日講(ごぼう講)」が行なわれ、講を行なう講主の名前が320年にわたって書き記されていて、私の先祖の「重右衛門」も名を列ねている。梅吉の妻志づ(旧姓藤井)は隣村の出身であった。
2021年(令和3)東京オリンピックフェンシングエペの団体で金メダルをとった見延和靖選手、海洋物理学の見延庄四郎北海道大学教授、札幌市議会議員だった見延順章さんも一族であることがわかった。
母方の祖母中山カツヱの先祖は、徳島藩洲本城城代家老稲田家に仕える郷士で、明治22年(1889)屯田兵に応募した。このときの家族は典子の高祖父(井川堅蔵)、高曽祖父母(井川惣介、ウマ)、養子を含む6名の子ども(典子の曾祖父井川宇八も含む)の計9名。
但し、政府迎えの船に無料で乗れるのは6名まで。そこで家族を二つに分けた。また屯田兵になれるのは30歳までなので、高祖父の井川惣介は井川嘉平と名前を変え、35歳を30歳に変えた。
屯田兵を継いだ曾祖父井川宇八が同郷の曽祖母サト(旧姓高田)と結婚したあと、同じ篠路兵村で暮らす屯田兵仲間の中山さんが土地を手放すことになった。開拓地の売買は禁止されていたが、養子(株養子という制度)になれば土地を入手できる。そこで井川宇八は中山姓に変え、名前も茂三郎とした。「井川宇八」がある日「中山茂三郎」になったのだ。生きていくために名前などなんの意味もなかったのである。
徳島時代の井川家の話を知りたいと思っていたところ、不思議なことが起きた。近所に住む長年のママ友とランチを食べていた時のこと。ルーツの話になって「徳島県の井川」という名前を出した。すると「あら、娘がこんど徳島の井川さんと結婚するのよ」という。もちろんそのお嬢さんも幼いころから知っている。結婚相手の舅さんが家系図をもっているというので、私のルーツとの接点がないか調べてもらったところ、なんと、私の高祖父(堅蔵)の名前があったのだった。ほとんどあり得ない話である。
おかげさまでというべきか、井川家が明暦期(1655~57)から現在の徳島県美馬市に根を下ろしていたことがわかり、同地にある先祖代々の墓所に参ることもできた。
母方の曽祖父長濵久松は、現在の石川県羽咋市の出身で、もとは「中屋」姓であった。先祖は妙成寺の塔中善住寺の檀家で、寺侍として前田家から扶持をもらっていたと聞く。そこで広島県立図書館へ行き、福井県にある氣多神社の文書を調べたところ、なんと「中屋」が載っている。1590年(天正18)の文書で、「殿様御手作分、いもほり」などと書かれていた。殿様とは前田利家で、食べ物の管理を任されていたのだから、信頼されていたのだろう。
「長濵」は久松の母の実家の姓で、母の実弟長濵万右衛門に跡継ぎがいなかった。そこで久松は叔父の万右衛門の養子に入って長濵姓になり、明治19年(1886)ころ北海道に渡った。そのころ同郷のよん(旧姓北出)と結婚している。
ほどなく札幌市白石にできた鈴木煉瓦工場で煉瓦職人として働きはじめる。ここで焼かれた煉瓦は北海道庁旧本庁舎(赤れんが庁舎)や札幌ビール工場(当初は製糖工場)でも使われた。白石の開拓史には必ず出てくる話である。
久松が長年書き綴った手帳は白石郷土館(白石区役所に隣接)で展示されている。また久松の長男は白石本郷商店街をつくるのに尽力した長濵万蔵(典子の大伯父)である。万蔵はさまざまな媒体で久松について語り、書いたので、多くのことが伝わっている。

この長濵家については、二従兄弟(曽祖父が同じ)の長濵好博さんと調査を進めた。他の縁者とともに現地羽咋での調査を二回行ない、冊子にまとめた。するとそれを読んでくれた篤志家が「鈴木煉瓦工場の所在地が、従来伝わっているJR白石駅ではなく、現在の白石区本通9丁目北(白石村87番地)であることは初めて知った。間違った説明板も正そう」といってくださり、さらに2025年6月14日札幌市コンベンションセンターで「鈴木煉瓦製造場シンポジウム」まで開いてくださった。
パネラーは鈴木煉瓦工場の鈴木豊三郎の子孫の鈴木清久さん、鈴木煉瓦工場のあった土地の最初の所有者の子孫大泉恒彦さん(タレント大泉洋の父)、郷土史家の杉浦正人さん、好博さん、私。かつての「白石村87番地」ゆかりの子孫が、およそ140年ぶりに一堂に会し、語り合ったのだ。200名の会場は満席になり、立ち見まで出た。

ルーツ探しの最後に残っているのは、父方の祖母の「菅谷家」である。祖母は「先祖は忠臣蔵の一人菅谷半之丞で、その子孫である私の父(見延の曽祖父)は山形県酒田市にある本間家で帳簿係をやっていた」と語っていた。討ち入り前に家族と縁を切っているので、どこまで先祖に辿れるかわからないが、「菅谷家」のルーツがわかれば私を作っている「ピース」はすべてはめられることになる。がんばりたい。

1955年、札幌市生まれ。
早稲田大学文学部卒業。『すっぽらぽんのぽん』で頼山陽記念文化賞。『頼山陽』で新田次郎文学賞。その他の著作に『もう頬づえはつかない』など。今回紹介したルーツの詳細は『私のルーツ』『私たちのルーツ』にまとめた。「頼山陽ネットワーク」事務局長。同ホームページ編集人。広島市在住。
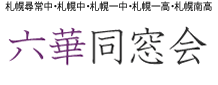

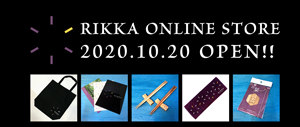


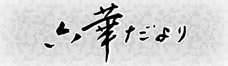
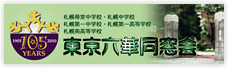

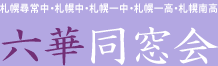
第107号 の記事
2025年10月1日発行