ウクライナ支援の現場から 学生ボランティアが見た世界
片貝 里桜(南67期)
はじめまして。東京外国語大学大学院(修士1年)在学中の片貝里桜と申します。
昨年(2022年)2月のロシアによるウクライナ侵攻は、全世界に衝撃を与えました。
大学でロシア語や東スラヴを学んでいた私は、戦争が始まって以降、ウクライナの方々へのさまざまな支援活動に携わってまいりました。この場をお借りし、印象に残っているヨーロッパでの避難民支援ボランティアの経験について、紹介させていただきたいと思います。
【ふるさとを追われる苦悩】
私は、いわゆる島民三世です。根室市に住む祖父は、第二次大戦終了時に北方四島に攻めてきたソ連軍により、故郷の色丹島を追われた経験があります。
連日ウクライナに関する報道に触れながら、元島民が紡いできた思いが私の中でウクライナの方々の姿と重なり、苦しむ人の助けにならなきゃという焦りに似た感情が生まれました。
日本では、国内に避難してきたウクライナの方々への通訳や、大学での反戦をテーマにした文化イベントの開催などを友人らと行ってきました。そんな中、昨年10月には避難民が多く滞在するヨーロッパへの渡航の機会をいただき、学生ボランティアとしてポーランドとオーストリアを訪れました。

【肌で感じた支援現場の温度】
私は、日本から一緒に訪れた仲間とともに現地のNPO団体の活動に混ぜていただき、さまざまなボランティアに参加しました。
世界最大数のウクライナ避難民を受け入れているポーランドでは、ウクライナから駅に到着した避難民の方々への案内や荷物運びのお手伝いをしました。
ウクライナ国境に近いこのプシェミシェル駅には、毎日早朝から深夜までウクライナから絶え間なく列車が発着し、大勢の人の往来があります。避難民の方々は、今後の生活で必要な日用品や大切な家財が入った荷物を一人で二個も三個もたずさえ、次の町へ向かっていきます。ずっしり重いスーツケースには、故郷にいつ戻れるか、もしかすると一生戻れないかもしれない不安と、それでも新しい土地で生きていかねばという覚悟が詰まっています。
プシェミシェル駅は、いつも緊迫感がありました。席数の少ない列車に我先にと他人を押し退けて乗り込む男性、頼れる身寄りがおらずその場に立ち竦んでいる高齢の女性、深夜の移動にすっかり慣れて戯れ合っている子どもたち———
そこにいる全員が自分のことで必死で、周りの人を気遣う余裕はありません。私は、逐一時刻表を確認しつつ行き先を聞いてプラットフォームに案内したり、支援物資の水や軽食を配って回ったり、休憩中には列車を待つ避難民の方と雑談をしたりしました。一方、めまぐるしく大勢の人が行き来する駅構内では、ボランティアの母数が足りないこともありました。どうしても一人一人にきめ細やかなお手伝いができず、限られた時間のなかで誰をサポートするかという小さなトリアージをせまられる場面もあります。
一方、オーストリアでは、首都ウィーンにある避難民向け滞在施設にて、食事の炊き出しのお手伝いをしました。この滞在施設は無料で食事を提供しているほか、国内での就労・住居の手続き支援も行なっています。いつも数十名の避難民の方々が滞在していました。ウィーン市の助成金で運営されているこの施設は、まだニーズがあるにもかかわらず、世界中から集まる寄付金や寄付品が徐々に減っており、閉鎖の可能性があるそうです。
施設では、オーストリア人のほか、アメリカ、中国、シリア、ロシアなど世界中から有志ボランティアが集まり、英語を共通語としてコミュニケーションを取りました。私も避難民の方とボランティアとの間で、英語、ウクライナ語、そしてロシア語を使って通訳を行いました。
ポーランドの駅とは違い、オーストリアの施設では人々の停滞感や閉塞感のようなものをうっすらと感じました。半年以上支援を続けているボランティアの一人が避難民に対し、彼らはタダのものだけもらって働こうとしないんだ、と愚痴をこぼす場面もありました。
また、すでに数ヶ月ウィーンに滞在している二十歳前後のウクライナ人の女性は、地元の大学を退学しなければならなかったことを同年代の私に打ち明けてくれました。オーストリアの大学では単位交換の制度がなく、入学金や授業料を用意できるかも分からず、無力感に襲われている、と。
戦争が日常化し、気づかぬうちに普通の生活が蝕まれていく恐怖。
他人の境遇を想像し思いやることができなくなっていく無気力感。
「世界がウクライナのことを忘れても、今も苦しむ当事者の存在を忘れないで」というNPO職員の言葉が胸に響きました。

【活動のなかで出会った優しさ】
私は、困っている人の助けになりたいという気持ちで支援を続けてきました。しかしながら、ボランティアを通して出会った方々から、むしろ自分が学んだことや得たもののほうがずっと多かったと思います。
残念なことに、侵攻から約一年半経過した今でも終戦の目処は立っていません。東スラヴ地域の民族や文化の豊かな多様性を無視して生んでしまった深い断絶がどれほどの憎悪を後世に残すだろうと考えると、本当に心が痛みます。現実に直面すると途方に暮れ、ちっぽけな学生の自分に何ができるだろうと無力感を覚えることもあります。
「日本から助けにきてくれたなんて、ありがとう」
ポーランドの駅で出会ったウクライナ人のおばあさんは、微笑みながら両手で私の手を包み込んでくれました。彼女の思いやりに触れた瞬間、心にぱっと火が灯りました。彼女と再会することはもうないかもしれません。けれど、「私たちは決して一人じゃない。きっといつかまた助け合えるよ」と、手の温もりが伝えてくれた気がしました。

片貝 里桜(かたがい りお)
1998年札幌生まれ。
東京外国語大学言語文化学部ロシア語専攻卒。同大学博士前期課程在学中。趣味は海外旅行、美術鑑賞。






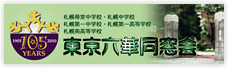


第103号 の記事
2023年10月1日発行